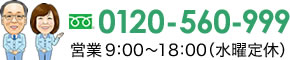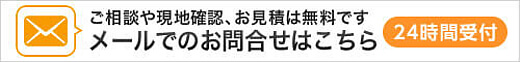桜と富士山を影彫りで表現した、オールインドM1Hのお墓!都立多磨霊園
東京全域でお墓のお仕事をさせていただいております、石誠メモリアルサポートの松本です。多磨霊園にて、桜と富士山を影彫りで表現した、オールインドM1Hのお墓を建立させていただきましたので、ご紹介いたします!

多磨霊園 新規建墓 2㎡クラス オールインドM-1H 影彫り
ホームページをご覧になったお客様がお電話でお問い合わせくださいました。多磨霊園の墓地に当選されて、お墓の建立をご希望でした。2㎡クラスの奥行きのある墓地です。お電話くださったのは娘様で、建立されるのはご実家のお墓とのことでした。現地でお会いしてお話を伺うと、弊社のホームページに掲載されていた同じくらいの広さのお墓を色々ご覧くださっていて、「このお墓のここがいい」といった具合で気に入られたところを組み合わせ、それをもとに図面を作成してご提案しました。

工事の様子です。床堀をして、基礎を打つ準備から開始です。多磨霊園でお墓の建立工事を行う際は、まずは管理事務所で敷地の正確な寸法を確認します。隣接墓域がある場合は、隣接するお墓から左右1.5cmずつ離してお墓を設置する決まりになっていますので、間口と奥行きを厳密に確認しておく必要があります。確認した寸法にあわせて床堀をしています。

掘り下げた場所にグリ石を入れて転圧して地固めします。

縦型のランマ―という機械でしっかり転圧し、強固な基礎になるように地盤を固めます。

型枠を組んで、コンクリートを打つ準備をしました。鉄筋も組みました。奥の四角いところは、土のままで仕上げる土残しです。

コンクリートを打ち、表面をきれいにならしました。このあと日にちを置いて養生します。

コンクリートがしっかり固まったら枠を取ります。基礎が完成しました。

カロートと外柵を設置しています。今回はお墓本体、外柵ともに、インド産のM1Hという濃い緑色の石をお選びいただきました。奥がカロート(納骨室)で、手前はお参りスペースです。手前左の袖石は墓誌を設置する場所です。

納骨室は、総御影石造りです。板石の上にお骨壺を並べて安置します。

石の継ぎ目はステンレス製の金具を入れて補強しています。

手前の開口部が土残し部分で、ここにも棚石を設置します。関東で一般的な7寸のお骨壺であれば、12個くらい納めることができます。この上にお墓を設置するため、ボンドを塗布して準備します。

台石を設置して、お墓を据えていきます。ボンドや免震ゴムパッドを使用して、耐震・免震施工で据えていきます。

このくぼみに墓誌板を設置します。最後に目地を打って仕上げ、お墓が完成です。

お墓本体、外柵まで、すべてインド産M1Hのとても美しいお墓が完成しました。M1Hは深い緑色がとてもきれいで、緑系の石をご希望の方には人気があります。日があたると鮮やかなグリーン、曇りの日は黒御影石のようなシックな色合いで、変化を楽しむこともできます。

棹石正面は「絆」の一文字です。 桜の花と富士山は「影彫り」という手法で表現しています。ちょうど近くにあった弊社の施工例に影彫りのお墓があり、とても気に入られて採用されました。

「絆」の字は梨彫りという彫刻方法です。文字のアウトラインを彫って、内側はふくらみを持たせています。素彫りのように深く彫り込まないので汚れも付きにくく、文字が鮮やかでどの角度からも見やすい点を気に入っていただきました。

「影彫り」は、小さな点で陰影を表現した彫刻方法です。花びらの一枚一枚まで、立体的に表現されています。
 花立の前面にも桜を彫刻しました。左手の墓誌は、袖石に埋め込む形で設置しました。間口が1m、奥行き2mの縦に長い敷地なので、囲いの内側に普通に墓誌を設置するとどうしても入り口が狭くなってしまいます。それでも囲いは欲しいというご希望を叶えるため、デザイン性を持たせて少し広く見えるような設計を試みました。当初は拝石を墓誌と兼ねるというプランもあったので拝石は手前に傾斜を付けていますが、墓誌の位置変更後もそのままの設計を維持し、水が溜まりにくい仕様になっています。
花立の前面にも桜を彫刻しました。左手の墓誌は、袖石に埋め込む形で設置しました。間口が1m、奥行き2mの縦に長い敷地なので、囲いの内側に普通に墓誌を設置するとどうしても入り口が狭くなってしまいます。それでも囲いは欲しいというご希望を叶えるため、デザイン性を持たせて少し広く見えるような設計を試みました。当初は拝石を墓誌と兼ねるというプランもあったので拝石は手前に傾斜を付けていますが、墓誌の位置変更後もそのままの設計を維持し、水が溜まりにくい仕様になっています。

完成後のお引き渡しにはご家族皆様がお越し下さって、皆様で記念写真を撮りました。陰彫りも素晴らしい出来栄えで、皆様にとても喜んでいただくことができました。桜も富士山も今回のために作ったデザインでしたので、実際の陰彫りがどういった仕上がりになるのかは完成してみないと分かりませんが、ご満足いただける素晴らしい仕上がりになり、私も大変うれしく思っております。このたびは、弊社にお墓作りのお手伝いをさせていただきましてありがとうございました。亡くなったお父様や、残されたお母様・ご家族様のためにも、後悔しない、納得のいくものを作りたいというお気持ちを叶えるため、できる限りのお手伝いをさせていただきました。皆様で末永くお参りいただければ幸いです。何かお困りの際は、どうぞいつでもお声かけください。
多磨霊園でのお墓の建立に関する記事
●最高級の銀杏面加工を施したスウェーデン産ファイングレインのお墓。都立多磨霊園2.8㎡区画
●多磨霊園にて、ステンドグラスから光が差し込む、インド産マハマブルーのお墓を建立!
●多磨霊園にて、赤城山を彫刻したインド産Y-1とアーバングレーのお墓。こだわりの通し階段
●根府川石の自然石のお墓の外柵リフォーム。富士山と桜の花、都立多摩霊園